
イラスト:ピストジャム
若月LOVE
平日の昼下がり。「レシピシモキタ」の前にあるリリーフランキーさん作のモニュメント「こいぬの木」の脇を通って、「モコモコ」というカラオケボックスに入る。
モコモコって。ずいぶんかわいい名前だ。「こいぬの木の脇を通って、モコモコに入る」。まるで絵本の世界の話みたいだ。
男二人でカラオケボックスに入るのは、いつになっても照れくさい。いや、年々照れくささは増している。もう二人とも四十路だ。しかも、店名はモコモコ。
40代の男が、昼から連なってカラオケボックスに入る姿は異様だろう。受付にいた若い女性店員は、顔には出していなかったものの、記帳した年齢を見て引いたはずだ。
どういう関係の二人? ただのカラオケ好きのおじさんたち? 平日の昼に来るって、仕事してないの? しかも利用時間、1時間って。足りる?
きっと気になっただろう。僕が店員なら、気になって途中でのぞきに行くと思う。
通された部屋に入り、とりあえずたばこを一服する。店員がすぐにアイスコーヒーを二杯届けに来る。
「ごゆっくりお楽しみください」
なんか嫌。個室にいる男二人に向かって言わんといてほしい。マニュアルで言ってるだけやろうけど、「ごゆっくりお楽しみください」って言われると、そういう関係やと思われてる気がして恥ずかしくなる。
おじさん二人、ちょっとはにかんで店員さんに
「どうもお」
「ありがとうございますう」
と、店員さんとは目を合わせていないが丁寧に答える。
「そう言えば、昔カラオケボックスで暮らしてたよな?」
「あんとき、マジできつかったわあ」
「そうやんな。結構長いこと暮らしてたよな」
「そうっすよ」
「どうする? もう一本くらいたばこ吸う? それか、もう始める?」
「じゃ、見てもらっていいすか?」
「いいよ。テーブル、端によけよか」
吉本の1年後輩に「若月」というコンビがいた。彼らは、兄・徹と弟・亮の兄弟コンビで、僕は二人とも仲がよかった。
最初の出会いは、2003年。神奈川県三浦海岸の住み込みの営業だった。
僕は、こがけんと最初の解散をしたのち、栃木県日光江戸村に4か月間の住み込み営業に行くことになった。それが終わると、今度は神奈川県三浦海岸のホテルに、また2か月間の住み込みの営業に行くことになった。
「ホテルで住み込みの営業」と聞いていたが、実際に宿泊する施設はホテルではなく、ホテルから徒歩15分のところにある木造の一軒家だった。若月の二人とは、そこで初めて出会った。
彼らはNSCを卒業後、東京のライブに出ることなく、すぐにそこに派遣されてやってきた。最初に挨拶されたとき、弟の亮は僕の目をしっかりと見て、
「俺たち日本一の漫才師になるんで。よろしくお願いします」
と、挨拶というより啖呵を切ってきた。
「よろしくお願いします」って、俺に言われても困んねんけど。でも、こんなにもストレートに自分の気持ちを言葉にするなんてかっこいい。気持ちいい奴だ。もしかしたら、売れる芸人ってこういう人たちなんかも。しびれた。
営業は過酷だった。夜に宴会場でネタを披露したりするのだが、お客さんは年配のかたが多く、芸歴1、2年目の僕たちには荷が重かった。余興以外にも、朝からいろいろとホテルの仕事をさせられたのもきつかった。ロビーの掃除、駐車場にやってくる車の誘導、宿泊客の荷物持ち、風呂掃除など、日中はホテルの従業員として働かされた。ジャンベという太鼓の体験教室のサクラをやらされたりもした。宿舎の一軒家も、芸人8人で泊まっているので、プライベートな空間はいっさいなく、寝るときはざこ寝だった。
1か月のギャラは6万円。源泉徴収で10%引かれて、5万4千円が振り込まれた。みな東京に部屋を借りたまま三浦海岸に来ていたので、これじゃ東京の部屋の家賃も払えないと嘆いていた。ここにいればいるだけ、赤字がかさんでいく。たまったもんじゃない。
毎晩、人前に立たせてもらえることはありがたい。しかし、生活がままならない。みな目に見えて、日に日に沈んだ顔になっていった。
僕は、最初から2か月間の約束だったので、なんとか耐えることができた。しかし、ほかの芸人たちは期限が決まっていなかった。いつまでこんな生活すればいいんだと自暴自棄になる奴がいたり、心を閉ざしたかのように誰とも話さなくなる奴がいたり。これはあとから聞いた話だが、この生活を5年間も続けた芸人もいたという。
僕は、三浦海岸を離れたあとも、たびたびその宿舎に顔を出した。若月が、腐ってしまうんじゃないかと心配だったからだ。
二人は、腐るどころか、おもしろさにさらに磨きをかけていた。いつか東京に戻ったときのためにネタをつくり続け、ずっと稽古していた。誰もいない砂浜で、海に向かって漫才の練習をしていたという。海に向かって漫才の稽古って。波打ち際で技の鍛錬する空手家やん。
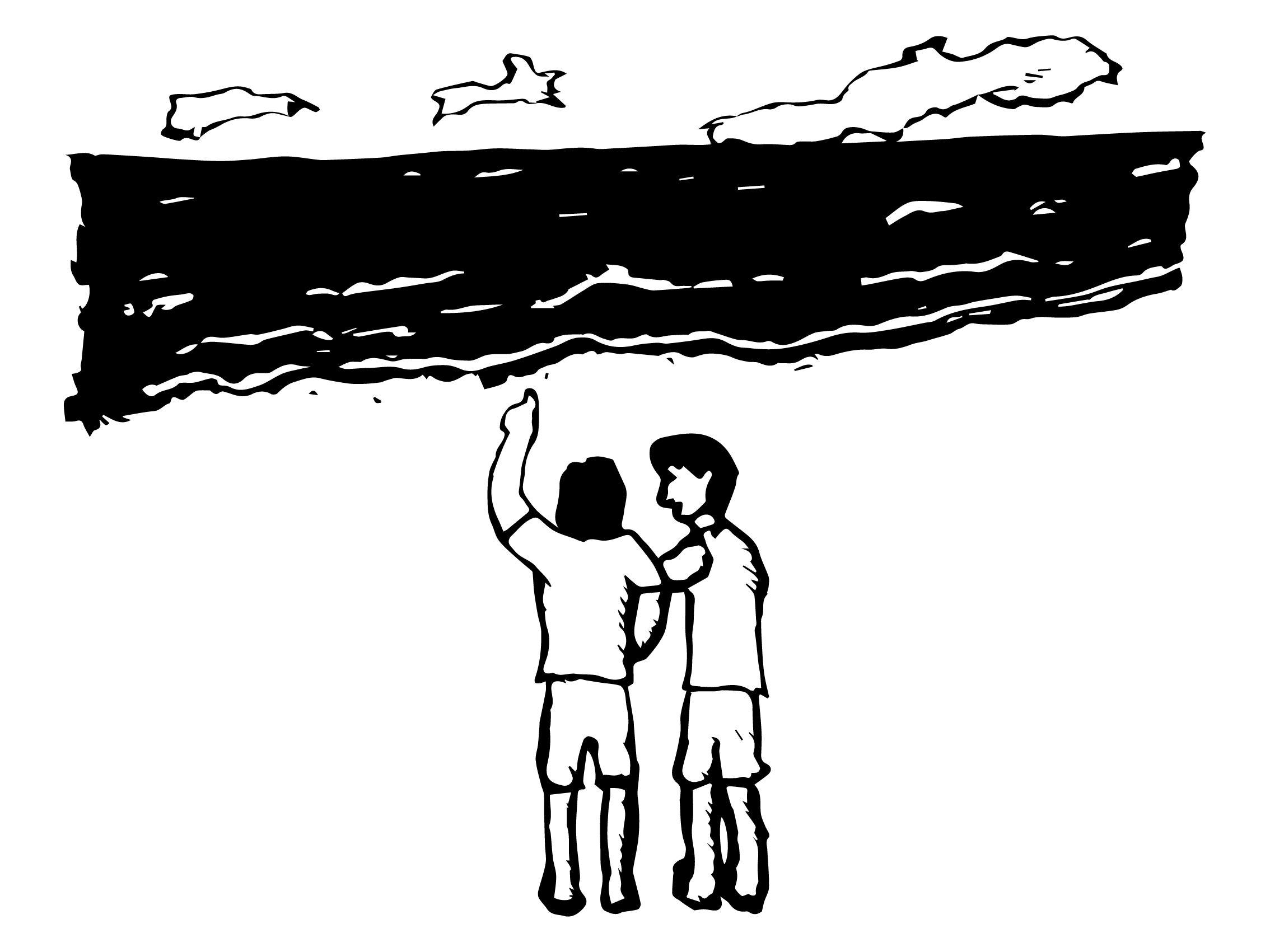
イラスト:ピストジャム
一年後、若月は東京に戻った。二人は着実に劇場の出番を増やしていき、人気を獲得し、ライブや舞台だけではなく、テレビや映画にも出演するほど活躍した。東京に戻って来てすぐに、徹がサンボマスターのMVに出演しているのを観たときには度肝を抜かれたものだ。
徹とは、よくシモキタでごはんを食べた。一番行った店は「とん水」。ここは学生のころからの行きつけだ。1972年創業で、今年50周年を迎える老舗。とんかつ屋なのに、いろんな定食があって、とにかくなんでもおいしい。チーズカツ、しょうが焼き、塩さば焼き、マグロフライ、肉ピーマン、ハムエッグ。ビールも飲むなら、冷やしトマトもいい。お米も、昔話に出てくるような大きな釜で炊いているので、米粒がひと粒ひと粒ふっくらとして輝いていて、甘みとうまみが凝縮されている。うまいのひとことに尽きる。ご夫婦二人で営業されていて、僕にとっては東京の親のような存在だ。実際、父がシモキタに来たときには、
「ここが、俺が東京で一番うまいと思う店」
と、言って連れて行った。父が、ご夫婦に
「息子がいつもお世話になってます」
と、挨拶していたのを覚えている。
徹を初めて連れて行ったときも、ご夫婦に
「後輩の徹です」
と、紹介した。すると、徹に
「彼女紹介してんじゃないんだから」
と、ツッコまれて照れた。
もう閉店してしまった「アンゼリカ」というパン屋で、名物のみそパンを買って、二人で公園で食べたりもした。喫茶店で、ネタの相談をされて何時間も一緒に考えたことは数えきれないし、煮つまって夜遅くに北澤八幡神社まで散歩したこともあった。
亮ともシモキタでごはんを食べた。ヴィレッジヴァンガードの向かいの「印度」というカレー屋でランチを食べて、こちらも行きつけの「いーはとーぼ」というジャズ喫茶に入った。
いーはとーぼは、1977年創業で今年45周年。こちらも老舗だ。店内はログハウスのようなつくりになっていて、経年変化した木々がなんとも言えない味を出している。10席あるかないかのこじんまりした店で、店主のおじさんがこれまたいい味を出していた。
初めて行ったとき、席に着いて注文しようと声をかけると、カウンターの中からものすごくだるそうな感じで
「へええい!」
と、大きな声で返事をされた。ちょっと怖かった。注文を取りに来たら来たで、今度はメモだけ取って、返事をせずに黙ってカウンターの中に戻っていった。なんやこの店。
別の日には、話が盛り上がって騒いでいる客がいた。すると、店主はコーヒーを淹れる手を止めて、わざわざカウンターから出てきて
「ここはジャズ聴く店だから!」
と、怒鳴った。その怒鳴り声のせいで、かかっているジャズが聴こえなかった。思わずツッコミそうになったが、もしそんなこと言ったら……と思ってこらえた。
そうかと思えば、まったくの別人かと疑うくらい、おとなしい日もあった。返事も、魂が抜けたような、うつろな声色。こちらが大きな声で話していても、何も言ってこない。
なんか今日は元気ないな。そう思いながら、最後会計のときに1万円札をレジで出したら
「お釣りないよ!」
と、いきなり怒鳴られた。いままで黙ってたんは罠やったんか!?
そんな感じが、僕は好きだった。コーヒーもおいしい。レコードの選曲も定番のものから攻めた民族音楽のようなものまで幅広く、聴いていて刺激的だった。くわえて店主のキャラも個性的ときた。
いかにもシモキタらしくておもしろい。頑固親父の家に、お邪魔させていただいているような感覚だ。
店内には、本棚のほかに、中古CDや古本、手づくりの小冊子などが置かれていた。あと、おもちゃの小さなピアノと、小学生が工作の授業でつくったような、謎の緑色のとげとげのかぶりものもあった。このかぶりものに関しては、本当に意味がわからない。だが、おじさんが怖すぎて聞けずじまいだ。
壁には、「いーはとーぼ〇〇周年おめでとう」という紙がいくつか貼られている。その「◯◯周年」のところには、上から紙が貼られて更新されていたり、マジックで書き直されたりしているのだが、どれも全部違う数字で、何が正解なのかわからない。ちなみに、前にスマホで調べて確認したら、どれも間違っていた。
最近は、おじさんではなく若い女性がカウンターに入っていることが増えた。もしかして、おじさん体調崩してるのかな。と、心配になったりする。が、これも罠の可能性あるな、と思ったりしている。
亮は、店内を見渡し
「ここ、ひとりでも来るんすか?」
と尋ねた。僕は
「うん。ひとりでも来るで」
と答えると、
「変わってますね」
とつぶやいた。
ひとりでシモキタを歩いているとき、女性から話しかけられたことがあった。その女性は、僕の正面から歩いてきていた。視線を感じたので目を合わせたが、知らない人だったのでそのまますれ違った。すると、その女性は
「すいません」
と、後ろから僕を呼び止めた。もしかして、これは逆ナンというやつか、と思って
「なんすか?」
と答えると、その女性は
「私、若月のファンです」
と言った。即座に
「あの二人最高ですよね」
と答えたが、気を抜いていたら
「は?」
と言っていたかもしれない。危ない危ない。
ほかにも、ライブ終わりに女性のお客さんから手紙をもらったことがあった。そこには、僕のことが好きだという内容が書かれていた。そして、文の最後には、連絡をくださいと言わんばかりにメールアドレスが書いてあった。
wakatsuki-love-foever@xxxxxx.ne.jp
誰が送るか。
僕からしたら、若月は順調に売れっ子芸人の階段を上っているように思えた。しかし、2014年の夏、二人は解散した。
解散に至るまでの間、僕は何度も彼らに解散を踏みとどまるよう説得した。おせっかいだとはわかっていたが、苦労をともにしてきた仲間が芸人を辞めてしまうのは受け入れがたく、止めずにはいられなかった。
でも、どうしようもないと頭ではわかっていた。出会ったころから、もう10年以上が経っていた。二人とも気づけば30歳を超え、亮は結婚して子供もできていた。
解散後、亮は就職して芸人を引退した。徹は、落語家に転身した。転身したと言っても、一からの出発だ。弟子入りし、師匠の付き人をしながら、3年以上前座を務めなければならない。30半ばにして、いままでのキャリアを捨て、新天地に飛び込むなんて。よっぽど勇気と自信がなければ、こんな決断はできない。僕には無理だ。現在、徹は二つ目に昇進し、三遊亭鳳月として立派に活動している。
「いいです、いいです。僕がやります」
「いや、別にええって」
二人でテーブルを端によける。
「今日のは、どんなネタなん?」
「これは『看板のピン』っていうやつなんですけど」
靴を脱ぎ、ソファの上に正座する鳳月。
「あ、知ってる。楽しみ」
「まだ覚えたてなんですけど。ちょっと気になるとこあったらダメ出ししてください」
「ダメ出しなんかあるわけないやん」
「いや、お願いします。じゃ始めます」
盛大に拍手。頑張れ、鳳月。モコモコ寄席、開演。

ピストジャム
1978年9月10日生まれ。京都府出身。慶應義塾大学を卒業後、芸人を志す。NSC東京校に7期生として入学し、2002年4月にデビュー、こがけんと組んだコンビ「マスターピース」「ワンドロップ」など、いくつかのコンビで結成と解散を繰り返し、現在はピン芸人として活動する。カレーや自転車のほか、音楽、映画、読書、アートなどカルチャー全般が趣味。下北沢に23年、住み続けている。
HPはこちら







