
イラスト:ピストジャム
お前さあ
「お前はさあ、根を張って生きようとしてんだよ。そういう奴なんだよ。俺らは、違うんだよ。俺らは、『明日引っ越しです』って言われても、すぐパソコンとネタ帳だけ持って引っ越しできる人間なんだよ。お前はできないだろ? だから、それが根を張って生きようとしてるって証拠なんだよ」
途中から話についていけなくなった。なんの話をしているのかよくわからない。
たばこの火を消しながら、なんとなくじゅんぺいのほうを見る。すると、彼は力なく
「そうですね」
と答えた。たぶんじゅんぺいも、もうこの話に飽きているんだろうと思っていたら、意外に落ち込んでいる様子で驚いた。
ちゃんと聞いていなかったが、「根を張って生きる」のがダメなんて話は聞いたことがない。普通は、「根を張って生きる」ほうがいいだろう。映画『レオン』のラストシーンだって、マチルダが鉢に入った観葉植物を地面に植え替える場面で終わっている。
高校ズの秋月が言ったセリフを反芻する。そこで、さっきの「俺ら」には自分も含まれていることに気づいて、あわてて
「俺は無理やで。パソコンとネタ帳だけ持って、すぐ引っ越しなんて絶対無理無理」
と割って入った。
いまはもうなくなってしまったシモキタ北口のガスト。僕と秋月とじゅんぺいの3人の組み合わせは珍しい。というか、初めてだった。
「またまたあ。野(の)さんは、完全にそういうタイプの人じゃないですかあ」
秋月が笑って返す。秋月は、僕のことを「野さん」と言う。「野」とは、僕の名字だ。
じゅんぺいは、話の矛先が僕に変わると
「確かに、寛志(かんし)さんはそういう人ですね。おもしろかったら、なんでもありって人ですもんね。部屋とかなくなっても大丈夫そう。生命力ありそうっていうか、しぶとそうですよね」
と、急に息を吹き返したように話し出した。
じゅんぺいは、僕のことを「寛志さん」と言う。「寛志」とは、僕の下の名前だ。
僕は二人それぞれと仲がよかった。秋月とじゅんぺいは、面識があるという程度でしっかり話すのは初めてらしかった。
「野さん、飲みもの大丈夫ですか?」
「あ、どうしよかな。もう5杯もアイスコーヒー飲んだしな」
「お前さあ、後輩なんだからそれくらい気づけよ」
「いや、そんな気遣わんでいいって。ドリンクバーくらい自分で行くし」
「すいません。僕が行きます。寛志さん、アイスコーヒーでいいですか?」
「お前、どんだけ野さんにアイスコーヒー飲ますんだよ」
秋月は吉本の1年後輩で、じゅんぺいは6年後輩だった。秋月とは二人きりで会うことがほとんどだったので、僕は彼の後輩としての顔しか知らなかった。
じゅんぺいに対して、先輩として振る舞う彼の姿は新鮮だった。僕は後輩に、「お前」と言ったことがない。それは小学一年生のころに「終わりの会」で、クラスメイトの女子から
「今日、野くんから『お前』と言われて嫌でした」
と訴えられて、司会の日直から
「じゃ、野くん謝ってください」
と、無感情なロボットのように指示されて、みんなの前で謝らされた経験があったからだ。
それがトラウマで、僕は「お前」という言葉を封印した。先輩らしく「お前」を巧みに使う秋月に少し嫉妬する。
「じゃ、何します?」
「なんでもいいわ」
「じゃ、アイスコーヒーでも?」
「アイスコーヒーはやめて。俺ここ来る前も秋月と喫茶店いて、アイスコーヒー飲んでてん。もう計6杯飲んでんねん。アイスコーヒー以外やったら、なんでもいいわ」
「お前、野さんが『なんでもいいわ』って言ったときの正解知ってる?」
「え? そんなのあるんですか?」
「メロンソーダに、ちょっとだけカルピス入れたやつだから」
「そんなん言ったことないわ」
「いやいやいや。この前、野さんが『なんでもいいわ』って言ったとき、僕がそれつくって出したら『うまい』って言って飲んでたじゃないですか」
「確かにおいしかったけど。でも、いまはそれを頼んだわけちゃうし。しかも、あのときは秋月が、『どうですか? ちょっと普通と味違うでしょ? うまいですか?』って何回も訊いてくるから、『うまいなあ』って言っただけやし」
「うわ、ショックだわあ」
「なんでショックやねん」
「じゅんぺい。これ、いまお前のセンス試されてるからな。お前が、いまから野さんに何を持ってくるか。これ試されてるぞ」
「試してないわ。じゅんぺい、ほんまに試してないからな」
「わかりました。アイスコーヒー以外ですね」
ドリンクバーに向かうじゅんぺい。彼の背中を秋月と見つめる。
じゅんぺいとは、バイト先が同じで毎日顔を合わせている。シモキタのピザハットで、今朝も一緒に働いていた。
彼の、笑うと目がなくなるところや、ぽっちゃりした体型は愛嬌があった。何かにつけて僕にいろいろと相談してくるところも、なんだか頼られているような気がしてうれしかった。
年齢も10歳離れていたし、本当に弟のような存在だった。ただバイト先では、その弟はシフトマネージャーという、いわゆるバイトリーダーだったので、バイト中は僕の上司だった。
「野さん、あいつ何持って来ると思います?」
「なんやろ。これでアイスコーヒー持って来たら笑うなあ」
「僕は、メロンソーダにカルピスじゃなくて、メロンソーダに紅茶とかオレンジジュースとか入れてくると思いますね」
「ああ、オリジナリティ出してくるパターンね。ありえるなあ。いや、俺は実験台か」
じゅんぺいは、いつもネタを考えていた。バイト中もネタ帳を開いて、ずっとネタを書いていた。
今夜はネタの相談をしたかったみたいなのだが、気がつくと話が盛り上がって、思わぬ方向に話がそれていってしまった。しかし、それはじゅんぺいのせいでもあった。
冒頭の会話は、じゅんぺいが秋月に恋愛相談をしたことが発端だった。じゅんぺいとしては、秋月と話したことがないし、ネタの相談をする前のアイドリングトークのつもりで、秋月に話しかけたんだと思う。
僕はその話を前に聞いていたので、その話題には参加せず黙っていた。でもその話は、いつの間にか結婚願望があるとか、ないとかの話になり、芸人としての心構えの話になり、どういった街に住むべきかという話になり、しまいには人として根を張って生きるのか生きないのかという謎のテーマに移り変わっていった。
時計を見ると、深夜2時をまわっていた。もうネタづくりはあきらめたんだろう。テーブルの上にあったネタ帳は、知らない間にリュックにしまわれていた。
じゅんぺいが戻って来る。手には、緑色の液体が入ったグラスを持っている。
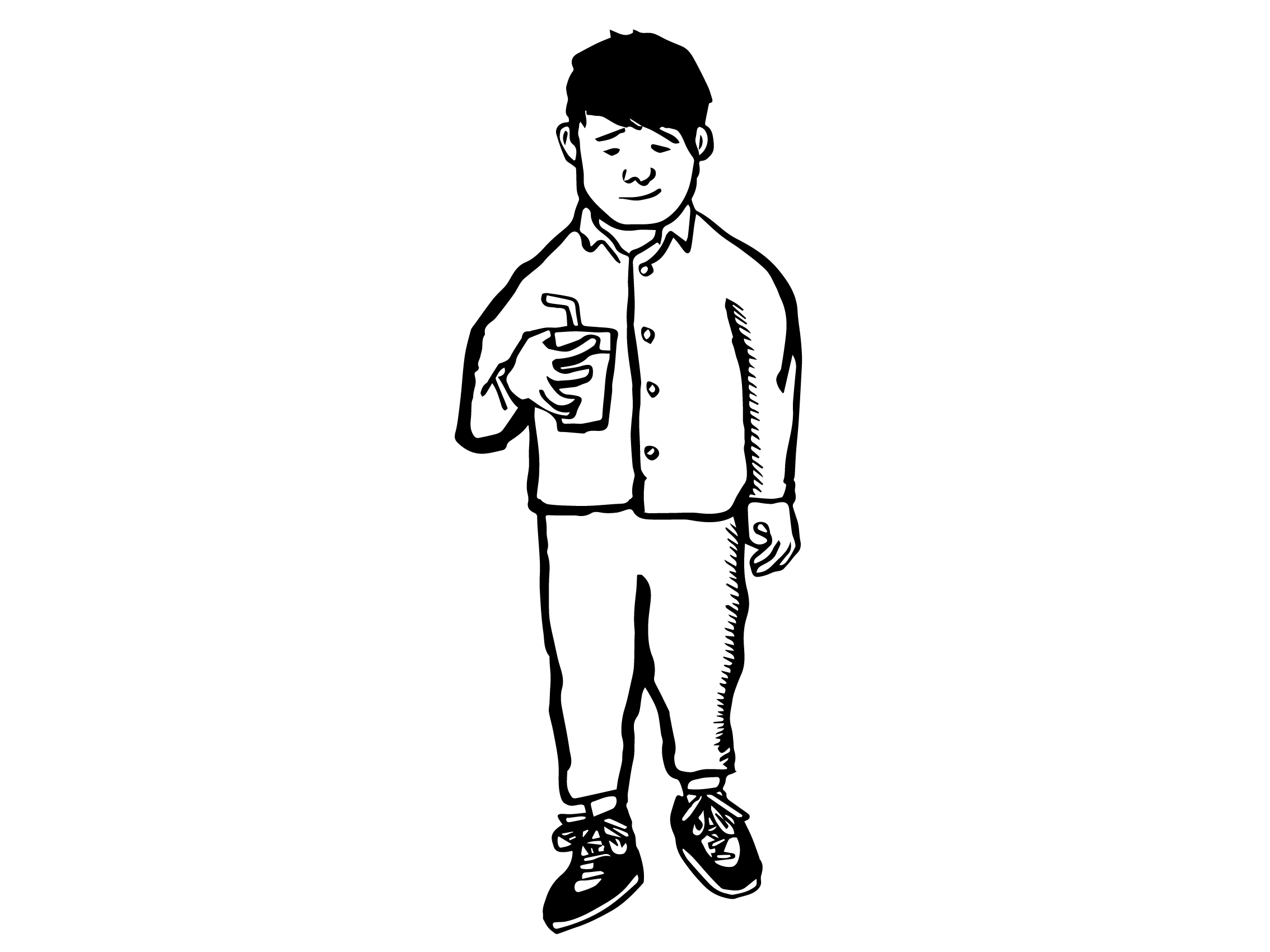
イラスト:ピストジャム
「ほらあ! あれメロンソーダでしょ!」
「もおお、じゅんぺい。ここはアイスコーヒーでよかってんてえ」
「お待たせしました」
「これ何? 普通のメロンソーダ?」
「飲んでみてください」
ストローで、ひと口飲んでみる。
「わからん。何これ?」
「秋月さんが言ってた、メロンソーダにちょっとカルピス入れたやつです」
「いや、お前さあ。そこはオリジナリティ出せよお。言ったとおりじゃなくてさあ。紅茶入れるとか、オレンジジュース入れるとか、いろいろあるだろ」
「どこダメ出ししてんねん。ていうか、なんでこんな変な飲みもん飲まされやなあかんねん」
「寛志さん、どうですか? うまいですか?」
「うん、うまいなあ」
「うまいんかい!」
じゅんぺいが笑いながらツッコむ。
じゅんぺいはこの数年後、相方のヒガ2000とケイダッシュに移籍し、コンビを解散したタイミングで芸人を引退した。
「お前さあ、これどうやってつくったの?」
「え? グラスに氷入れて、カルピスちょっと入れて、メロンソーダ入れましたけど」
「それ違うから。メロンソーダ入れてから、カルピスだから」
「ええ! なんすかそれ」
じゅんぺいは芸人を引退したのち、すぐに結婚した。秋月が言ったとおり、根を張って生きる人間だった。
「カルピスは重みがあるから、最後に入れたら自然に下におりて行って、いい感じに混ざるんだよ」
「どっちでもいいわ!」
思わずツッコむ。秋月が口に人差し指をあてて、小声でつぶやく。
「野さん、ちょっと声大きいです。ほかのお客さんもいるんで」
「おらんやろ! 貸切やんけ!」
「寛志さん、どうですか? うまいですか?」
「何回訊くねん!」
またストローで、ひと口飲む。
「うん、うまいなあ」
「うまいんかい!」
じゅんぺいも秋月も、楽しそうに笑っている。

ピストジャム
1978年9月10日生まれ。京都府出身。慶應義塾大学を卒業後、芸人を志す。NSC東京校に7期生として入学し、2002年4月にデビュー、こがけんと組んだコンビ「マスターピース」「ワンドロップ」など、いくつかのコンビで結成と解散を繰り返し、現在はピン芸人として活動する。カレーや自転車のほか、音楽、映画、読書、アートなどカルチャー全般が趣味。下北沢に23年、住み続けている。
HPはこちら







