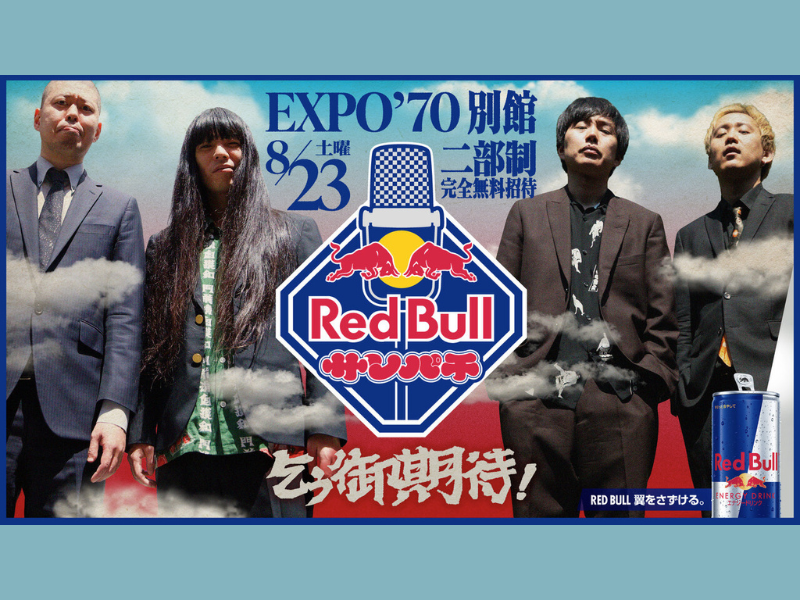ノーベル平和賞のソーシャルビジネス
4月16日、地域課題をビジネスで解決するソーシャルビジネスコンテスト「島ラブ祭」が那覇市の琉球新報ホールでガレッジセールとハイビスカスパーティーのちあきの司会で行われました。島ラブとは沖縄の島ぜんぶをソーシャルビジネスで覆いつくそうというムーブメント「島ぜんぶでうむさんラブ」の略称で、沖縄を良くしていきたいという強い思いを持つ15組が参加し、2022年1月に発足しました。当初は思いが先行していた15組でしたが、ビジネスに落とし込むべく、ソーシャルビジネスとは何か、自分はどういう人間か、というところから学び、お互いに刺激しあいながら4か月が経ち、今回、そのなかの14組がコンテストでの発表に臨みました。

ソーシャルビジネスと聞くと、貧困や教育、環境汚染など社会課題をテーマにするため難しそうなイメージがありますが、島ラブは沖縄の言葉で面白い、ワクワクすることを意味する「うむさん」が込められ、吉本興業ホールディングスの発案で生まれたことから親しみやすく、社会課題を身近に感じられる特徴があります。また、大きく2つの点で注目されてもいます。そのひとつが休眠預金を活用した先駆的な事業であること。そしてもうひとつが、貧困層、特に女性たちに資金を無担保で融資するマイクロクレジットによって起業を促し自立の道筋をひらいた、2006年のノーベル平和賞受賞者ムハマド・ユヌス博士の考え方に基づいた手法を取り入れているところです。
コンテストに先立ち、一般社団法人ユヌスジャパン代表理事で、九州大学の特任教授である岡田昌治氏からユヌス博士のソーシャルビジネスの7つの原則が説明されました。その原則とは、ビジネスの目的を一般企業のように利益の最大化ではなく、貧困、教育、環境等の社会問題を解決することをはじめ、投資家は投資額までは回収できるが、それを上回る配当を得ることはできないことや、経済的な持続可能性を担保すること、ジェンダーと環境に配慮すること、そして何より、楽しみながら事業を行うことなどが紹介されました。

続いて、ユヌス博士から届いたビデオメッセージがスクリーンに流され、「貧困は発展途上国だけの問題ではなく、先進国にもあり、沖縄も避けられない問題であること、また、その解決のために医療や教育、失業といった問題に対し、ビジネスで解決していこう、金融サービスさえあれば、誰もが起業家になれる」ということに続き「この島ラブのプロジェクトを成功させ、島を豊かにしていきましょう」と語りかけられました。

コンテストは島ラブの14組が4組ずつ発表。練習したとはいえ、慣れないプレゼンテーションに苦労する発表者には、会場から「がんばれ~」といった声援も聞かれ和やかなムードで発表は行われました。発表のなかには、働きたくても働けないシングルマザーと人材不足で悩む建設業界の課題を、AIを活用し建設業界の仕事をアウトソーシングすることで両者の課題解決につなげる事例や、琉球大学発のベンチャーで、CO2の分離、回収技術と、回収したCO2を海ブドウの養殖に活かすといった世界課題の解決に通じる事例がある一方で、待機児童や保育士不足、障碍者福祉、引きこもりなど、地道な取り組みが求められる人の課題に取り組む事例が多く発表されました。
他にも廃棄問題や農業の課題に取り組む事例や、農家の土壌のすばらしさを活かしたいといったもの、先人が育んだ野草の知識が失われていることや、島んちゅの優しさが逆に自分の感情を押し殺す原因になっているといった沖縄ならではの課題まで、事業のステージも取り組む課題も多岐にわたっていました。その一方で、東京などの大都市のビジネスコンテストと違うのは、誰かの想いを背負い課題に挑んでいる事例が多いこと。亡き弟や亡くなった夫、困っていた時に救ってくれた人など、誰かのために、誰かの役に立ちたいといった気持ちが伝わるプレゼンテーションが多く、ビジネスモデルを聞きながら、涙ぐんでしまうのは、この島ラブの魅力と言えます。
グランプリは社会に適合せずに適合する「アシタネプロジェクト」

すべてのプレゼンテーションが終わり、コンテストのグランプリである「島ぜんぶでうむさんラブ賞」は会場に来ていた約250名の観客が投票します。その集計の間に、ゲストのアーティストであるSatoly(サトリー)さんが登壇しました。世界19か国の孤児院や盲学校、養護学校などでアートを通じて自立を促す活動が紹介され、先駆者に勇気を与えました。その後行われたコンテストの総評では、立教大学の西原文乃准教授が、「これまでの社会は人と人、人と環境などを分断してきたのではないか、そして参加者の皆さんはそれらを共存共栄していこうとされているのだと感じました」と述べ、今後の沖縄のソーシャルビジネスについては、ソーシャルビジネスの先駆者である竹中ナミさんが「沖縄の人のあたたかさやゆったりとした時間といった“らしさ“を大事にしてほしい」と述べる一方、地元のみらいファンド沖縄の平良斗星副理事長は、沖縄の相互扶助を意味する「ゆいまーる」という言葉の本来の意味である「支援する側と支援される側が相互に支えるようになれば、もっとソーシャル活動は活発になる」と、未来への希望を述べました。
司会を務めたガレッジセールのゴリが、「みんな自分をさらけ出していたから、心にすんなり入ってきた」と言う通り、参加者の皆さんは誰もが自分をさらけ出していましたが、グランプリには、もっとも自分をさらけ出したであろうアシタネプロジェクトが選ばれ、投票総数の半分近くの票を集めました。
アシタネプロジェクトは、自分たちを社会不適合者で社会と馴染めず引きこもりであった経験を語り、仲間のひとりである山城結花さんの「美味しいコーヒーを飲んでほしい」という思いを皆で実現しようと、苦手な接客にも挑戦し、自分たちが変わっていったことを朴訥と、でも一生懸命に話す姿が支持を得ました。
グランプリの記念品として、参加者たちと同様に時を経るごとに熟成される泡盛が贈られ、手にしたメンバーの國吉秀樹さんは、「当初は他の人と比較してしまって、自分たちは役に立てていないんじゃないかと思ったが、3か月目くらいにそれでもいいのかな、と思い始め、いまは以前とは違う自分になれたのかな、と思います」と語ります。

プレゼンターである吉本興業ホール―ディングス会長でユヌス・よしもとソーシャルアクション社長でもある大﨑洋は、アシタネプロジェクトについて「ビジネスモデルでみればまだまだだと思いますが、そもそもユヌスさんとユヌス・よしもとソーシャルアクションという会社をつくった時に、ビジネスという言葉に違和感を覚えてアクションにしたくらいですから、いいと思います」と祝福。岡田先生も「コンテストで涙したのははじめて」だと述べ、これほどのエネルギーのある島ならばソーシャルビジネスアイランドに必ずなる」と確信した模様。
「ゆいまーる」や「模合」といった人と人が支えあう沖縄の歴史と、吉本らしい人の心を動かす文化がうまく組み合わさったからこそ、「島ラブ祭2022」は、他ではみられない優しく、共感されるソーシャルビジネスのコンテストになりました。

以下、発表者のダイジェストです。
***************************
島ラブの14組が4組ずつ発表。
1組目は、地元の新聞社が地域のプラットフォームを目指し、2組目は農家さんの土の魅力を伝えたいと家庭菜園キットの販売。
3組目は待機児童の問題解決のために、保育士資格の取得サポート。そして4組目は沖縄のエネルギー自給率2.7%を解消するために、エネルギーの地産地消を目指すことなどが発表されました。
続いて、2番目のグループでは、5組目が障碍者が感じる「社会との壁」を取り払うためにアートを通して個々の理解を深め、障碍を個性に変えようとし、6組目は、働きたくても働けないシングルマザーの問題と建設業界の人材不足をAI活用で建設業界の仕事をアウトソーシングし、両者の課題を解決していきます。
続く7組目は、学生が廃棄に目を向けようと、微生物を活用したコンポストで生ごみを減らしていくビジネスプランを発表。8組目は、琉球大学発のベンチャーで、CO2の分離、回収技術と、回収したCO2を海ブドウの養殖に活かすという世界的課題の解決に通じるもの。
休憩の後、9組目は異例でした。不登校支援を行う予定の大学生チームは、ほんとうに自分たちが解決できる課題はこの問題なのかと悩み、本番の2週間前にビジネス化を断念。その心情を語ります。続く、10組目は吉本興業所属の比嘉竜太が、沖縄で29年育ってきて、感じる違和感をショートコントで表現し、人と違うことを嫌がる、自分の感情を押し殺す風潮を「ありのままの自分を大切にする」活動につなげていく小学生を対象にした漫才ワークショップとして発表しました。続く11組目は、沖縄の道端に自生する「さし草」が、カルシウムやビタミンA、鉄分、ポリフェノールなど、豊富な成分をもつところに目をつけました。
12組目は維持が難しい学童保育をテクノロジーでサポートする伴奏型の支援であり、13組目は、自分たちを社会不適合者だと感じていたグループが、仲間の美味しいコーヒーを飲んでほしい、という気持ちをサポートすることで、社会とつながっていけたことを発表。
最後は、日本の社会福祉の実践家である糸賀一雄氏の「この子らを世の光に」を実現しようと障碍者福祉に取り組むチームの発表でした。