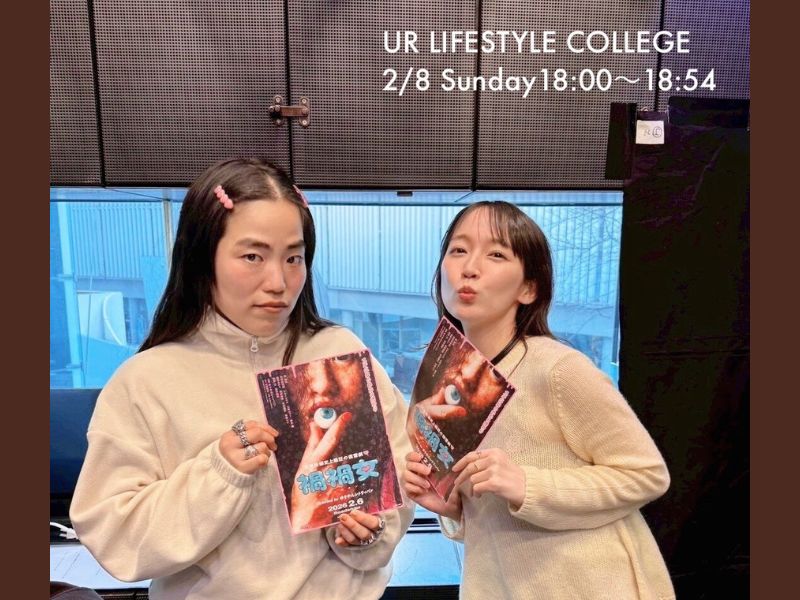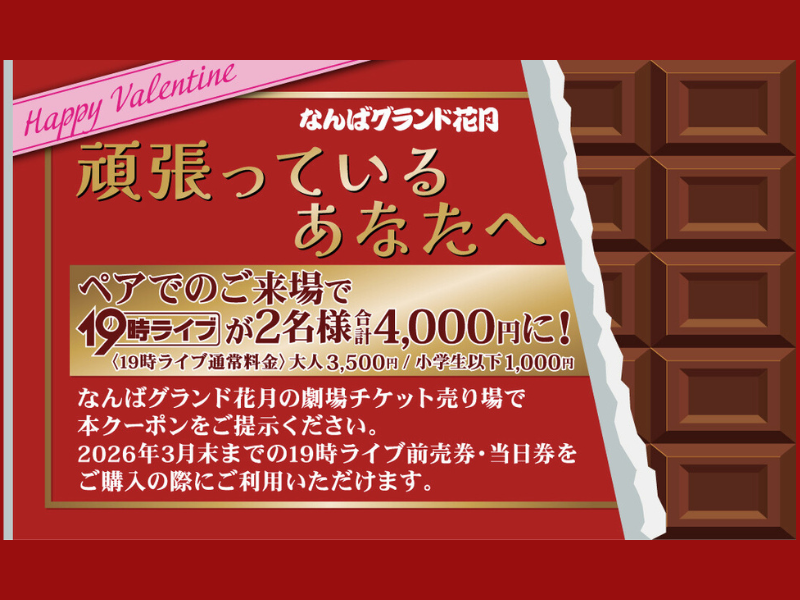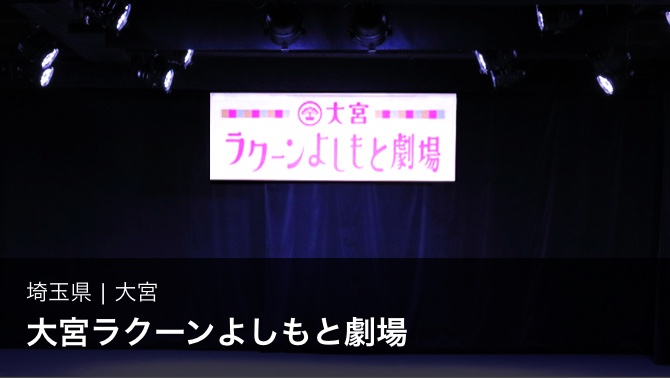Google Cloud主催のイベント『AI Agent Summit ’25 Fall』が、10月30日(木)に都内で開催されました。AIエージェントの現在と未来を考察するというビジネスリーダー向けのいたって真面目なイベントに、なんとマヂカルラブリー・野田クリスタルが登壇! 今年4月に自らプロデュースしたAIプラットフォーム『無限大喜利』をローンチさせた野田は、さまざまなトラブルを乗り越えてきた開発の秘話や、AIを活用して日本のお笑いを世界に展開する可能性について大いに語りました。

「大喜利欲」が抑えられずAIプラットフォームの開発に着手
お笑いの舞台とはかなり雰囲気が異なる、東京・渋谷のイベントホール。AIについての知見を深めようと集ったビジネスマンたちが熱心に見つめるステージに、野田クリスタルが「どうも、こんにちは!」と、手を振って登場しました。
講演のテーマは「野田クリスタルが挑む、AI とお笑いは仲良くやれるのか?」。野田は冒頭、「R-1チャンピオン、M-1チャンピオンです!」と自己紹介をして拍手を促すと、自身がプロデュースした大喜利プラットフォーム『無限大喜利』について話を始めました。
「皆さん、大喜利ってやったことありますかね?」と会場に問いかけた野田。自身はインターネット上で誰でも参加できる「ネット大喜利」サイトに投稿していた経験があるほど「大喜利愛」があるといいますが、最近はテレビを含め、大喜利を目にする機会がめっきり減ってしまったと指摘します。

「(自分の)大喜利欲も湧いているし、みんなもやりたいんじゃないか」――そんな理由で開発をスタートしたのが、AIを使った大喜利のプラットフォームでした。
このイベントにも登壇したFANYのエンジニア・山本泰之氏とともに完成させた『無限大喜利』は、AIが24時間、自動でお題を生成してくれるという画期的なプラットフォーム。制限時間内にユーザーが回答を投稿すると、見に来たユーザーたちによる投票によって順位がつけられます。
今年4月のローンチから半年間で65万件の解答が投稿され、面白い答えに対しては、なんと122万票もの支持が集まったとのこと! なかにはたった1人で、半年間に1万回もの回答をした“つわもの”なユーザーもいるとか。野田は「何をされてる人なんでしょうか、心配です僕は」と、会場の笑いを誘っていました。

お題が「ゴリラ」ばかりになるトラブルも
順調に見えた『無限大喜利』ですが、ローンチ後には「とある問題」が発生していたと野田は振り返ります。
ある時期を境に、「飼育員がゴリラに土下座! 一体何があった?」「動物園の飼育員だけが知っているゴリラの秘密とは?」など、なぜかゴリラに関するお題が大量発生するようになってしまったのだとか。
エンジニアの山本氏も「ゴリラが出まくっているなと、チームで把握はしていました」と真面目な顔で答えつつ、お題生成のシステムについて専門的な解説を挟みます。
対策を講じたことでユーザーの投稿回数が微増したり、回答数ゼロのお題が減ったりという効果があったものの、今度は「この社長、草食系だな……。どんな社長?」「社長が号泣、何があった?」などと、なぜか「社長お題」の乱発が起きてしまったとか。

さらなる対策とチェックのシステムを入れるなど地道な改修を繰り返したことで、こうした問題は解決。投稿数がそれまでの2倍になるなど、たび重なるピンチを乗り越えてプラットフォームが成長していったストーリーが語られました。
一連のトラブルをきっかけに、野田は「いいお題とは何か」を考えることになったそう。結果、「こんな◯◯は嫌だ」と形式がかぶるのは構わないが、「ゴリラ」「社長」といったキーワードがカブるのはきついこと、また、たとえ単語がカブっていなくても、答えづらいお題というものがあることを認識したといいます。
「これまでニュアンスで考えていた『いいお題』について言語化できるようになった」という野田。「大喜利に関してエキスパートである僕ら芸人と、エンジニアが相談しながらやっていくことが大事」だと語ります。そして、開発を通して得た気づきについて、こうまとめました。
「時代の流れや大喜利のトレンドによって『いいお題』は変化していく。(問題は)一生解決しないんだろうなと思いました。だからこそ、常に限りなく100%に近づけ続けることが、AIと芸人のともに取り組む作業なんだと思います」

AIのサポートでお笑いが進化する未来
『無限大喜利』では今後、現代の大喜利で定番のテーマと言える「写真で一言」の実装や、回答分析機能の導入などを考えているといいます。
野田は今後のAIに期待することとして、大喜利の答えそのものではなく、ベストな答えを導き出すためのサポートの役割を挙げました。
「たとえば、『このアナグマ、SNSでバズりそうだな……なぜそう思った?』というお題に対してアナグマの知識を教えてくれるとか、AIにアシストをしてもらいたい。答えじゃなく、導き出すための補助をしてほしい。それが芸人としてAIに求めるものですね」
さらにその先の展開として、世界を見据えた“夢”を語りました。
「大喜利は文字だけだから、(回答者の)声や見た目や知名度が関係ない。ということは、世界共通でできるはず。海外の人を大喜利で笑わせてみたい。そのためには、AIの力が使えるのではないか?」

今回の講演のテーマは、「お笑いとAIは仲良くやれるのか?」。これについて野田は、「AIと芸人に限らず、ニュアンス的な職業とAIとのかかわり方が、今回の開発を通して見えてきた」と指摘。「エキスパートである芸人をAIがサポートしていけば、お笑いがとんでもないコンテンツになるんじゃないの?」と語ります。
一方で、お笑いは「言語化したらつまらない文化」でもあり、また常に新鮮である必要もあります。学習して育つAIには新鮮なものを生むのは難しいという弱点もある、と課題点も挙げた野田は、最後にこう会場に呼びかけて、講演を締めくくりました。
「このジレンマを誰が解決するんでしょうか? 最強のAIを作る人がいるんでしょうか? AIとお笑いに興味がある人があればお声がけください」